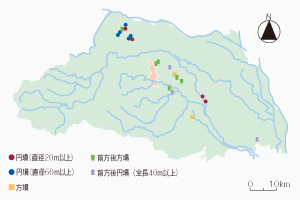嵐山町web博物誌・第4巻「嵐山町の原始・古代」
2.古墳時代前期
大和政権の誕生と勢力の拡大
3世紀後半から4世紀代を古墳時代前期と区分しています。大和政権(やまとせいけん)誕生の時代ということができます。舞台となったのは、奈良県北方の奈良盆地東南部、三輪山(みわやま)の麓。ヤマトと呼ばれるこの地域には、箸墓(はしはか)古墳をはじめ超巨大な前方後円墳が集中し、大王の都にふさわしい大規模な遺跡群が展開します。
『古事記』や『日本書記』の記述によれば、「朝廷が四道将軍(しどうしょうぐん)を派遣して各地の勢力を従わせた」ということです。この時期はまさに大和政権の誕生と勢力の拡大期にあたります。
- 奈良盆地の前期古墳と纒向遺跡
-
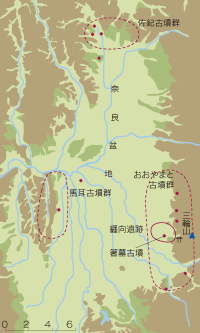 奈良盆地を取り囲むように、3〜4世紀にかけての初期の前方後円墳が分布しています。中でも全長200mを超える箸墓古墳をはじめとする多くの古墳が集中する纒向遺跡とその周辺は、まさしく初期大和政権の中枢であったと考えられています。
奈良盆地を取り囲むように、3〜4世紀にかけての初期の前方後円墳が分布しています。中でも全長200mを超える箸墓古墳をはじめとする多くの古墳が集中する纒向遺跡とその周辺は、まさしく初期大和政権の中枢であったと考えられています。
- 古墳時代前期の土師器(纒向遺跡出土、奈良県立橿原考古学研究所附属博物館・桜井市教育委員会提供)
-

纒向遺跡は、1kmを超える範囲に拡がる大規模な遺跡群で、大和政権の都といっても遜色のない都市遺跡です。 - 纒向遺跡出土の東海系土器(奈良県立橿原考古学研究所附属博物館提供)
-
 この遺跡での大きな発見は、九州から関東に至る各地で作られた多くの土器でした。地方の物資や人々が参集する政治・文化の中心地であったことを裏付けています。
この遺跡での大きな発見は、九州から関東に至る各地で作られた多くの土器でした。地方の物資や人々が参集する政治・文化の中心地であったことを裏付けています。
- 初期古墳の分布図
-
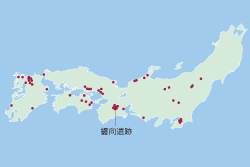 纒向型と呼ばれる初期の前方後円墳は、瞬く間に全国へと広がります。それは、祭祀の形態を共有することで地方の政治勢力が大和政権に次々と参画していくことを意味すると考えられています。
纒向型と呼ばれる初期の前方後円墳は、瞬く間に全国へと広がります。それは、祭祀の形態を共有することで地方の政治勢力が大和政権に次々と参画していくことを意味すると考えられています。
嵐山周辺はまだ弥生的
嵐山町では、4世紀代の古墳はありません。この時期は、まだ弥生時代の伝統を受け継ぐ方形周溝墓が依然として造られていました。しかし比企地域や隣接する熊谷市などでは、方形周溝墓に加えて前方後方墳形周溝墓や前方後方墳が造られ始めています。
この古墳も弥生時代色の強いものですが、規模が格段に大きく、それだけの労力を動員できる、強い勢力を持つ首長が成長していたことを意味しています。ただし旧来の墓の形態を踏襲するこれらの首長たちは、大和政権からの直接的な影響はあまり受けていなかったと考えられます。