嵐山町web博物誌・第7巻【祭りと年中行事編】
風祭り
笠懸の弓矢を濡らす秋しぐれ 種村武徳
暑い夏を追い払うように、台風はやってきます。そしてまるで、二百十日の走り穂を狙い定めたかのように。
いつもと向きの違う、湿気を含んだ重い風―鈍い鉛色に沈む空―だんだんと強まる雨足―この半年の汗の結晶を一夜にして失う恐怖―眠れない夜。
自然のなせる技に、人はあまりにも無力です。それでも、人は祈ります。田に風切りの鎌を立て、夜通し経を読み、先祖の霊を供養します。
生きるため、明日に命をつなぐための、少し悲しい風の祭です。
1.二百十日|家の行事,稲作の行事

青々と生長した稲。その背景には長期にわたる農家の人々のたゆまぬ努力がうかがえます。
立春から数えて二一○日目は、「二百十日」と呼ばれています。この時期になると、田んぼの稲の生長も佳境を迎え、実りの秋を待つばかりとなります。「二百十日の別れ水」とむかしからいわれたように、田の水を落として稲の完熟目前までこぎつけ、まずはひと安心といったところですが、この季節は台風の脅威にさらされることが多く、一瞬の暴風雨で「二百十日の荒れじまい」という結末になる恐れもあり、農家は気が気でありませんでした。そこで、二百十日のころは各地で風水害の防除を祈願する行事が行われます。
嵐山町遠山では、この日まんじゅうを作ってお日待ちを行いました。
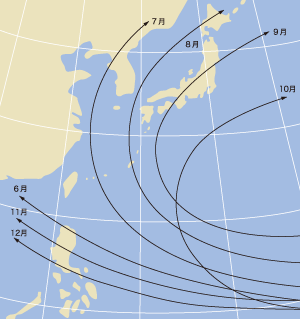 月別の台風の主要経路(原図:熊谷地方気象台 1996『埼玉県の気象百年』)
月別の台風の主要経路(原図:熊谷地方気象台 1996『埼玉県の気象百年』)






