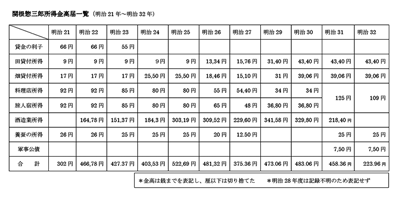第6巻【近世・近代・現代編】- 第3章:産業・観光
第5節:商工業
関根惣三郎(小島屋)の酒造業
飲酒の歴史は人類の誕生と共にあったと言われている。酒は「御神酒(おみき)」と称されて祭祀に不可欠でもあったし、戯言に「お神酒あがらぬ神はない」等と言って、人間誰しもが酒を飲むことを当然とする生活習慣が蔓延していった。これに呼応するように鎌倉・室町期頃より酒を造る者も多く現れ、それらの中には巨利を得る者もあったので、室町幕府は酒屋役(酒壷銭・酒壷一固につきいくらというように課した税)を設けて税を課した。江戸期に入っても1697年(元禄10)、「酒運上金」と言い、1772年(安永元)、「酒造役」と称して酒に課税している。この様に早くから行政が課税の好対象とする程に酒造・酒販の利益率は高かったのであろう。維新直後も酒造人の取調べが早々おこなわれている。中爪村大惣代本多藤右衛門からの回達文によれば酒造人があれば名主同道で出頭するようにと触れている。新政府は課税好対象の酒造人を逸早く把握したかったからであろう。
明治に入ってこの地方にも本格的な酒造業者が現れた。その一例が菅谷の関根惣三郎である。彼が比企横見郡長に提出した「所得金高届」によると1889年度(明治22)に「酒造業所得」164円78銭と届けられている。前出の所得金高届を1887年(明治20)から1899年(明治32)まで所得別一覧に作表したものが、次に示した「所得金高届一覧」である。この表によれば1888年(明治21)には酒造業所得は計上されていないので、1889年から操業されたものと考えられる。
1891年(明治24)、惣三郎は名古屋の里見五郎兵衛から酒造に大切な水について新発明の秘伝を教わっている。一つは「防腐水ノ伝」(火止メノ法)と、もう一つは「割水ノ伝」(寿齢水)の二つである。「火止メノ法」はサリチールサン・ホウシャを沸騰した湯(極上の清水)に溶解させたものを防腐水として新酒に加えれば「一ト火モ入ルニ及ズ決テ腐敗スル愁ヘナシ」と言うのである。又、「割水ノ法」は紅花(こうか)・細辛(さいしん)・ナツメ・山梔子(くちなし)・唐辛子・粒コショウ等々約十一味の薬種を並酒一升五合に加えて一升に煮詰め、それに清水十五倍を加えて薬水を製する。この薬水は薬種の五味(ニガキ味・シブキ味・カラキ味・アマキ味・スキ味)を含でいるので、これを適宜原酒に加えることで甘口・辛口等微妙な酒の味の違いを醸成出来ると言うのである。かくして惣三郎は色々酒造研究の結果、銘酒「小錦」を世に出した。
所得金高一覧表によつて見ると1892年(明治25)以降の酒造業所得は前年(明治24)に比して飛躍的に高くなっている。また他の田畑貸付所得や料理旅館業の所得に比べても酒造所得の占める割合は高く、収益性の高い生業であった。しかしそれには多くの資本が投ぜられてもいた。1892年(明治25)の「酒造資本額調」によれば合計1028円30銭と報告されているが、この時期の千円は大金であった。明治初期一両は一円と考えていた。文化文政期(1804〜1829)、一両の価値は米なら三俵(十二斗)分と推定され、三両もあれば大人一人一年位生活が出来たという。明治になっての物価の変動を考慮に入れたとしても、その額の巨大であったことが理解できる。
この様にして順調に滑り出した酒造業ではあったが、1898年(明治31)4月類焼によって多大な損害を蒙ることになってしまった。1898年(明治31)の「酒類蔵出帳」の末尾に4月11日調査として検査員立合いの上「焼失石数147石5斗5升5合」と報告されている。この年の査定石数が186石2斗4升8合となっているので凡そ八割を失ったことになる。他に建屋・器材等も失ったことであろう。前出の「所得金高届一覧」によれば1898年(明治31)には酒造業所得が半減しており、翌99年(明治32)には全く計上されていない。酒造業を中断せざるを得なかったのであろう。いまや小島屋の銘酒「小錦」は幻の存在となってしまった。